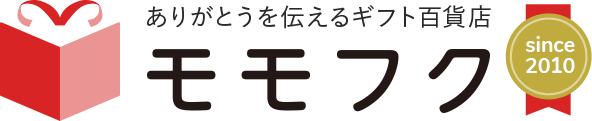引出物も地方ごとにさまざま
結婚式にも地方によって異なる風習やしきたりがあるように、引出物もそれぞれの地方で特徴があります。引出物には、地方ごとに贈るものの種類や贈り方など、さまざまな違いがあります。ここではその違いについてご紹介していきます。
特徴的な引出物!地域によってどんな違いがある?
引出物といえば、縁起物。全国では縁起を担ぐためにどんな引出物が用意されているのか、特徴的なものを中心に見ていきましょう。

お祝いの象徴、紅白まんじゅうや紅白餅
石川県や兵庫県では引出物に紅白まんじゅう、鳥取県や滋賀県では紅白餅を贈る風習があります。兵庫県の淡路島では引出物の紅白まんじゅうを「嫁入りまんじゅう」と呼んだり、滋賀県の長浜市周辺では紅白餅を「おちつきぼた餅」と呼んだりします。

佐賀名物まるぼーろや千代結びは幸せの形
「まるぼーろ」はカステラと同じ生地で作る丸い形が特徴的な和菓子です。丸い形は角がないことから「角が立たない」といわれ、縁起がよいとされています。
「千代結び」は水あめを加えて作る砂糖菓子で、佐賀市を中心とした佐賀県の伝統菓子です。千代結びは無限を表す「∞」の形に似ており、切れ目のないことから「いつまでも幸せが続く」という意味があります。どちらも縁起物として佐賀県で引出物によく用いられています。

おいりの丸い形は夫婦円満の象徴
「おいり」は、香川県西讃(せいさん)地方から愛媛県の東伊予地方一帯で引出物に用いられる、縁起物のお菓子です。おいりは丸い形をした小さな米菓子で、ひなあられのようなものです。カラフルな見た目が華やかさを感じさせます。豆のような丸い形から「まるい心でまめに働く」といった意味が込められています。

梅干しは夫婦が長く続くことの願掛け
和歌山県では名産品の、梅干しが引出物にもよく用いられます。梅干しを食べるとすっぱさで顔がシワシワになることから、「シワシワになるまで夫婦が一緒に歩んでいけるように」、「シワが寄るまで元気に過ごせるように」という夫婦円満や長寿を祈る意味が込められています。

和菓子やかまぼこにも縁起物
岩手県や三重県、石川県などでは、昔から縁起がよいとされている、鶴や亀などをかたどった和菓子を引出物として贈ります。富山県では縁起物の富士山や鯛をかたどったかまぼこを贈る風習が残っています。半円型のかまぼこは日の出を連想させることから、門出にふさわしいとされています。
引出物の贈り方も地方によってさまざま
引出物の種類だけでなく、贈り方も地方によってそれぞれ特徴があります。愛知県や岐阜県、新潟県には、新郎新婦の名前を入れた風呂敷に、複数の引出物を包んで贈る風習があります。この風呂敷は愛知県や岐阜県では「名披露(なびろう)」や「名披露目(なびろめ)」と呼ばれ、新潟県では「松の葉」と呼ばれています。
これらは新郎新婦の名前を知ってもらうという意味のある伝統的な風習です。しかし現在では簡略化し、風呂敷やタオルに新郎新婦の名前を入れた熨斗(のし)をつけて贈ることが多いようです。
品数や金額にも地方によって差がある
愛知県の名古屋市では、引出物は重くてかさばるくらいがよいとされています。一方で、北海道では1,500円前後の比較的リーズナブルな引出物が一般的です。これは北海道の結婚式が会費制であり、ご祝儀を贈る習慣がないためだと考えられます。
このように引出物には地方ごとに風習やしきたりがあります。最近では風習にこだわらない人も増えていますが、その土地ならではの引出物を取り入れることで年配の方にも喜んでもらえます。引出物を選ぶ際の参考にしてみてはいかがでしょうか。